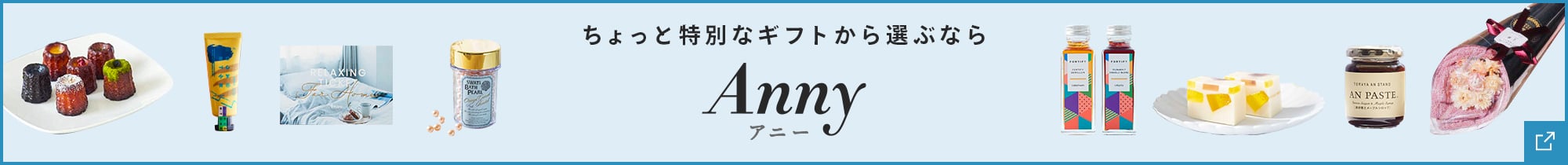- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様
【蔵出】亘理隆胤 三江 「七絶詩」◎肉筆紙本◎佐沼亘理家五代当主 亘理伊達家9代 佐沼城最後の当主 伊達家臣 登米郡佐沼町初代町長
-
商品説明・詳細
-
送料・お届け
商品情報
【蔵出】亘理隆胤 三江 「七絶詩」◎肉筆紙本◎佐沼亘理家五代当主 亘理伊達家9代 佐沼城最後の当主 伊達家臣 登米郡佐沼町初代町長 商品詳細 商品寸法:全体 186㎝ × 78㎝本紙 134㎝ × 64㎝◎肉筆保証◎紙本掛軸◎軸先:木◎木箱付【亘理隆胤】 (1848-1916)佐沼亘理家五代当主。亘理伯耆基胤の子。通称は大吉。号は三江、古鹿山人。嘉永元(1848)年3月15日、誕生した。文久2(1862)年、父・基胤の隠居にともなって家督相続。大吉このとき十五歳。元服にあたっては、宗家の伊達邦隆を烏帽子親とし、「隆」字を給わったと思われる。慶応4(1868)年の奥州では、朝敵として追討の対象になっていた会津藩・庄内藩を救うべく、仙台藩・米沢藩が中心になって、薩長主体の奥羽鎮撫総督府と交渉を行っていたが、交渉は遅々として進まず、閏4月11日、仙台藩・米沢藩が盟主になって、会津藩救済を求める二十七藩からなる奥羽列藩同盟が結成されて強い態度で交渉に出た。しかし、世良修蔵、大山格之助ら私的に会津・庄内を恨む薩長藩士が参謀として権力を握る軍隊において、列藩の努力は踏みにじられることになった。こうした中、世良は「奥羽皆敵」として討つことを書状に認めて大山に送ろうとして仙台藩士に発見され、閏4月20日、二本松の楼閣の土蔵にいたところを捕縛されて阿武隈川の河原において斬首。列藩同盟と総督府は敵対関係となった。5月23日、仙台藩は梁川播磨を大隊長とする五小隊を新庄に出兵させた。これは出羽久保田藩に同盟離脱のうわさがあったためで、庄内藩の救援という名目で派遣されたものであった。また、参政の但木左近、中村宗三郎は出羽との国境・寒風沢と尿前の守衛を命じられている。そして7月4日、仙台藩から秋田藩へ遣わされた使者十一名が秋田藩士によって斬殺され、秋田藩は列藩同盟を離脱し、庄内藩に攻め寄せた。7月10日、仙台藩大隊長・梁川播磨は、庄内藩・水野弥兵衛、米沢藩・樋口甚六らとともに、新庄藩隊を先鋒として庄内へ向かっており、及位(真室川町大字及位)に片倉大之進隊・秋保助太郎隊の二小隊と米沢藩二小隊を配置し、そのほかの列藩兵は蟻谷・大瀧に配置していたが、7月11日朝、佐賀藩の大砲隊、佐賀藩・小倉藩の歩兵隊が山を越えて奇襲してきた。片倉、秋保、樋口隊らは不意を討たれて第二胸壁へ退いて抗戦したものの、新庄藩の寝返りもあって同盟軍は敗退。仙台藩大隊長・梁川播磨は佐賀藩士・石井弾三郎に狙撃されて負傷し、同じく負傷した軍監・五十嵐岱助とともに刺し違えて自刃。ほか三十六人が戦死を遂げた。 これら大敗の報告を受けた仙台藩庁は、国境守備に出していた岩出山伊達家の三小隊を庄内へ増派することとし、但木左近・中村宗三郎隊を遊軍として控えさせた。これに加えて、今村鷲之助を軍事参謀とした軍勢の派遣を決定。仙台在府の亘理大吉隆胤も出陣を命じられた。 7月15日、隆胤は国元の佐沼に出兵を命じる使者を派遣し、これを受けた佐沼の留守居は二百七十名の一大隊を整えて出羽へ向けて出立。翌16日、仙台から出兵してきた隆胤と中新田(栗駒市栗駒八幡)にて合流。19日、中新田を出立して岩出山城下(大崎市岩出山)に宿陣した。家老職の坂本助左衛門、中村惣右衛門以下、佐瀬源吾(旗奉行)、牧野半助(番頭)、翁新兵衛(銃隊長)、伊藤吉之助(兵糧奉行)、今野蔵治(参謀)、狩野金右衛門(監軍)、野川惣吉・氏家末之進(古銃隊長)、畑中昌平・今野常吉(武頭)、武川文太夫(大筒隊長)ら総勢三百八人の軍勢を整えた。 さらに涌谷伊達隊(亘理東吾隊、坂本半左衛門隊)、船岡柴田隊(銃士五小隊)、瀬上主膳(三小隊)の兵がこれに加わっている。米沢藩からも本荘大和隊(宮島掃部参謀)七百名が合流している。 7月21日、岩出山を出立して鳴子温泉(大崎市鳴子温泉)に宿陣。24日、鳴子温泉を出立して、一気に山を登って新庄藩領瀬見温泉(山形県最上郡最上町瀬見温泉)に入り、28日、新庄藩領長沢村(最上郡舟形町長沢)に宿陣。8月3日、激戦場だった船形村(舟形町舟形)の宿場町に陣を構えた。 しかし、このあたり一帯はすでに戦いは終わり、8月3日には焦土と化した新庄城下(新庄市)を通過して新庄藩公戸沢家の菩提寺・瑞雲寺(新庄市十日町)に本陣を置いた。翌8月4日、新庄を出立して北上、及位峠(真室川町大字及位)の西軍陣所跡を踏み渡り、院内(湯沢市上院内)に宿陣した。このあたりに来ると、秋田藩との戦いの前線に近づいてきていた。 8月7日、庄内藩と連携し、東側の間道を北上するルートを進むこととなった隆胤は、この日は稲庭(湯沢市稲庭町)に宿陣。翌8日早朝に出立したが、八連村(湯沢市駒形町八連)ではじめて敵兵と遭遇。涌谷隊先手の銃隊長・翁新兵衛が攻めて、増田村(横手市増田町)まで追撃し、銃士隊の近藤兵衛、今野蓮治、大砲銃隊・阿部友吉の三名が負傷したが、亘理勢は秋田藩兵を追い落とすことに成功。戦勝の勢いは翌9日も続き、亀田村、半助村でも大勝を収めて増田に帰陣した。 その後も列藩同盟軍の攻勢は続き、秋田藩の南の要・横手城を包囲した。この包囲戦では、涌谷伊達家の軍勢が城の南を、隆胤率いる亘理勢は南西を固め、南東からは瀬上主膳、西からは主力の庄内藩勢がそれぞれ攻め立てた。隆胤と瀬上主膳は搦手の橋際まで進むと、さかんに銃撃を加えた。十九歳の城代・戸村大学は奮戦したものの、ついに及ばず血路を開いて落ち延びていった。この戦いでは、番頭の牧野半助、鑓隊士の千田半兵衛、銃隊士の佐々木保之進、伊藤忠治らが抜刀して功名を挙げた。しかし、銃隊長の翁新兵衛が止めるのも聞かずに伊藤忠治はさらに敵を深追いし、伏勢の銃撃を受けて戦死した。これが亘理隊の初の戦死者となった。忠治の遺体は、ともに奮戦していた笛士・伊藤仲が駆け寄って収容し、横手の頼光寺に埋葬された。その後、忠治の父で兵糧奉行の伊藤吉之助が遺体を荼毘に伏して佐沼へ送ったという。 横手を攻め落としたのち、続いては要害・角館を攻めるべく、庄内、涌谷、佐沼勢はさらに北上した。そして8月14日、金沢宿(仙北郡美郷町金沢)を通過して六郷(美郷町六郷)に宿陣。16日、六郷を出発して、大曲宿に着陣した。17日、角館攻めの評定が行われ、庄内藩から北爪楯六、加賀山藤太夫が軍監として佐沼勢に加わっている。 8月18日、大曲から四ツ屋(大仙市四ツ屋)に陣を進め、8月20日、川沿いの合田渡で敵の間者を捕えている。 8月21日、佐沼隊は仙台藩の瀬上主膳とともに四ツ屋を出て、東の横沢(大仙市太田町横沢)へ移った。四ツ屋は仙台藩将・中村宗三郎(岩ヶ崎領主)が守衛していたが、24日未明から始まった激戦に敗れ、涌谷勢・岩出山勢とともに六郷まで退却した。 一方、佐沼隊は23日午前六時、隆胤は古銃隊長・氏家末之進を隊長とする一部隊を斥候として先陣させ、国見村(大仙市太田町国見)に入ったとき、一面に広がる萱原の中から敵の伏兵による銃撃を受けた。この報告を受けた隆胤はただちに手勢を国見に向かわせて合戦に及んだ。これに瀬上主膳の部隊も加わり、敵の大村藩勢を大いに打ち破った。この合戦で大村藩士・葉山平右衛門以下、大村喜兵衛、溝延寿太郎、片桐小一郎、中山半槌、野木新蔵らが抜刀して突撃してきたが、佐沼隊鑓士・千田半兵衛、仙台本藩監軍の草刈鉄之丞・内海雄一郎、瀬上主膳の家臣・岩淵左覚らによって掃討された。しかし、この合戦で佐沼銃隊隊長・氏家末之進をはじめ、菅野千代治、高橋謙治、佐々木文左衛門、阿部勝之進、三浦養蔵、佐藤円太夫が討死、高橋千代治、氏家周蔵、佐藤富治が負傷した。 佐沼隊は瀬上主膳隊とともに角館へ向けて進軍し、国見で激戦。8月24日、いったん横沢に戻り、さらに板見内(大仙市板見内)に本陣を移して、横沢には守衛の一小隊を配置して守った。ここで岩ヶ崎中村隊、岩出山伊達隊と合流し、8月28日、佐沼隊は瀬上主膳隊とともに角館城の東、白岩前郷村(仙北市角館町白岩前郷)に進軍し、西軍と合戦となった。川を挟んでの激戦であったが、佐沼隊ほか仙台藩・庄内藩兵は敗れ、板見内にまで退却を余儀なくされた。この合戦で佐沼隊の足軽目付・岩崎十助が討ち死にしている。 その後数日の間、佐沼隊は板見内に宿陣し、その周辺にいた西軍との散発的な戦闘を繰り返した。一方、岩出山伊達隊、涌谷伊達隊、岩谷堂伊達隊、水沢伊達隊、庄内藩兵らは角館に向けて進軍を開始していたが、9月17日、佐沼隊のもとに仙台藩の降伏を伝える伝令が到着した。 このころ仙台城内では、和平派と主戦派の二派に分かれて激しく争っていたが、9月9日、和平派の水沢領主・伊達将監邦寧、亘理領主・伊達藤五郎邦成らが主戦派の奉行・但木土佐、坂英力らを退け、藩論を恭順降伏と定めた。こうして仙台藩も西軍に降伏することとなり、藩公・伊達慶邦は伊達将監と宿老・遠藤文七郎允信を降伏の使者として総督府に派遣。9月15日、仙台藩の降伏が認められた。伝令はこれを受けたものだった。 9月18日、停戦の使者として、大町源十郎が佐沼隊の陣所に到着。ただちに兵を仙台に戻すよう指示を受け、隆胤は板見内を陣払いして、21日にかけて稲庭、小安(湯沢市皆瀬)、田代(湯沢市皆瀬)と険峻な栗駒山系を横断、沼倉(栗駒市栗駒沼倉)でようやく一息つくことができたという。その日のうちに、岩ヶ崎(中村宗三郎知行地)に到着し、ここで一泊。翌22日、隆胤は軍事参謀・今村鷲之助、家老・中村惣右衛門、参謀・今野蔵治、馬廻・伊藤謙吉らとともに仙台へ向かうこととなり、佐沼隊は9月23日、坂本助左衛門に率いられて佐沼に帰着した。 隆胤は維新の後は、学区取締、駒方神社宮司権大講義、岩木山神社権宮司などを拝任し、初代佐沼町長に選ばれ、地元の名士として活躍している。 武勇の人である一方で、涌谷伊達家の私学校・月将館や江戸の昌平校で学び仙台藩学・養賢堂の教授となっていた大槻盤渓や国分松嶼、岡千仞らに経史詩文を師事し、学問にも深い造詣があった。 大正5(1916)年10月20日、六十九歳で惜しまれつつ亡くなった。法名は静観院殿博誉文英仁公大居士。◎商品状態特 上 中 下☆ ☆ ★ ☆ 発送詳細 ◎送料負担:落札者◎ゆうパック着払い(お品物サイズより別運輸会社の利用可能性が有)◎発送元:関東、関西、東北及び九州地方数箇所 支払詳細 【Yahoo!かんたん決済 】-Yahoo!マネー/預金払い-クレジットカード-インターネットバンキング-ジャパンネット銀行支払い-銀行振込-コンビニ支払い 注意事項 ◎お品物は無事に受け取りでしたら、お手数ですが、必ずヤフオクに当商品ページに「受け取り」ボタンをお押しください。◎掛軸書画品◎真作は保証しないので、価値判断、状態(オレ・シミ・イタミ・その他)は画像でよく御確認の上ご入札ください。タイトルや作家詳細はこちらの能力で落款や在銘よりつけて、真作か模写か、ご自分自身でご判断ください。当方は責任を負いません。目立つダメージは明記しておりますが、画像では見にくい細かなダメージがある場合がございます。説明しきれない時代物としてのシミ・イタミ・シワ・剥脱・ヤブレ・ヤケ・変色等見られます。特に記載がない場合、箱等の付属品は画像にあるものが全てです。当方、誠実に出品しているつもりでございますが、中には商品の見間違いなどある場合も時にあります。※返品不可 ご了承ください。◎評価、同梱、領収書につきまして◎お客様への評価は、全体的に入れときます。当方への評価を頂ければ、ありがたいです。評価不要のお客様は落札される際にご連絡ください。 同梱希望、または領収書希望でありましたら、落札後にご遠慮なく、ご連絡ください。◎落札頂いた後、落札者様よりのご連絡がなく5営業日が過ぎ、ご入金もない場合は当方にてキャンセルさせて頂き、ヤフオクシステムにより、悪質な落札者と判断、自動的に「非常に悪い落札者」と評価し、ブラックになります。ご了承ください。◎商品画像は受け取り後削除します。受け取りしない場合は発送後より最長7日間残し、7日を過ぎますと削除されます。予めご了承下さい。◎金額の誤入札の取り消し、キャンセルはお受けできません。よくご確認の上ご入札をお願いします。いたずら入札を避けるため、評価の合計が-1以下の利用者の入札、または「非常に悪い・悪い」の評価の割合が多い利用者の入札を取消する可能性があります。
残り 1 点 12480.00円
(125 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 07月20日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
-
ラッピング
対応決済方法
- クレジットカード
-

- コンビニ前払い決済
-

- 代金引換
- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
-
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)
-